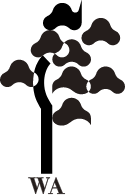越前漆器 Echizen Lacquerware
Echizen lacquerware originated Fukui Prefecture.
Traditional Japanese craft,
A history going back more than 1,500 years.
-
漆器とは、うるしの木から採取された樹液、もしくは、樹液を精製した「漆」を、木の器に塗り重ねて作る工芸品です。
縄文時代の遺跡から漆器の使用が確認されており、その歴史は非常に古くまでさかのぼります。
漆は、その堅牢性や耐久性、加飾のしやすさから、さまざまな用途に用いられてきました。日常生活でよく使われる漆器には、汁椀や重箱、茶道具などがあります。
また、仏像や神社仏閣の建物、芸術品などにも漆が用いられています。
-
漆を塗り重ねることで上品かつ艶やかな塗り肌があり、また、軽さと丈夫さも兼ね備えています。
越前漆器は、素地づくり、塗り、加飾等の様々な生産工程が高度に専門化されていることも特徴の一つです。
分業体制の確立により、美しさ、堅牢さと言った、品質の安定と、高い生産能力に繋がっています。
<生産工程>
1:木地製作
木地製作は、漆器の土台となる木材の加工を行う工程です。丸物は水目桜、トチ、ケヤキなどの木材をろくろで削って形を作り、角物はカツラ、ホオ、漆器用合板などを裁断して組み立てます。木地製作は、漆器の強度や耐久性に大きく影響するため、熟練した職人の手作業で行われます。
2:塗り工程
塗り工程は、木地に漆を塗って仕上げる工程です。
下塗りと上塗りがあり、下塗りは漆の密着性や耐水性を高めるためのもので、上塗りは漆器の表面を美しく仕上げるためのものです。塗り工程は、均一に塗る熟練の技術や、漆の乾燥を適切な温度と湿度で行う技術が求められます。
3:加飾工程
加飾工程は、漆器に模様や絵を描く工程です。
蒔絵や沈金などの伝統的な技法を用いて、美しい装飾を施します。
加飾工程は、職人の高度な技術と感性が求められます。
-
越前漆器の起源は、約1500年前までさかのぼります。
継体天皇が、越前国(現在の福井県)の片山集落を訪れた際、冠を壊してしまい、その冠を修理を塗師に命じたところ、塗師は漆を用いてみごとに冠を修理しました。
さらに黒塗りの「三ツ組椀」を献上しました。
その出来栄えに感動した継体天皇は、片山集落での漆器の生産を奨励しました。これが越前漆器の始まりと伝えられています。
越前は山々に囲まれた土地で、古くから漆掻き(漆の木から樹液を採取する職人)が多くいたこと、良質な材木が採れたこと、温度や湿度も漆器づくりに適した環境であったこともあり、この地では漆器づくりが発展していきました。
優れた技術と美しさが評価され、古くから皇室や貴族に愛用されてきました。